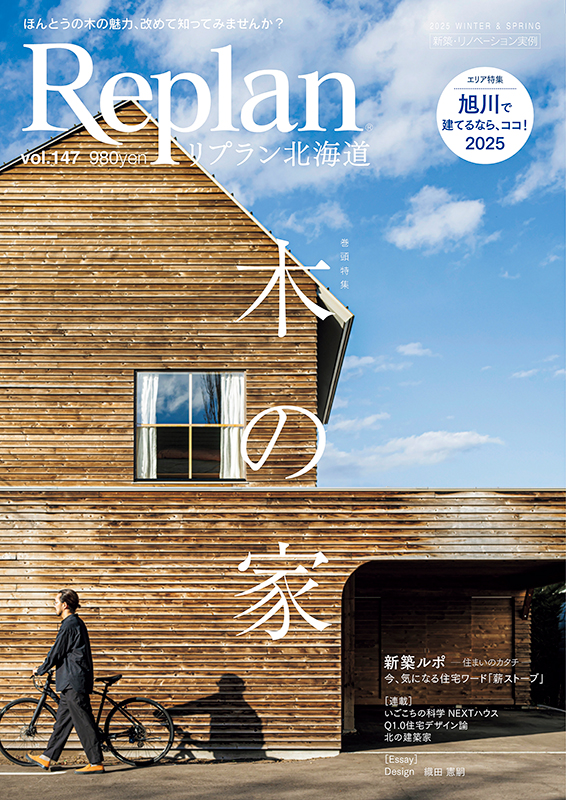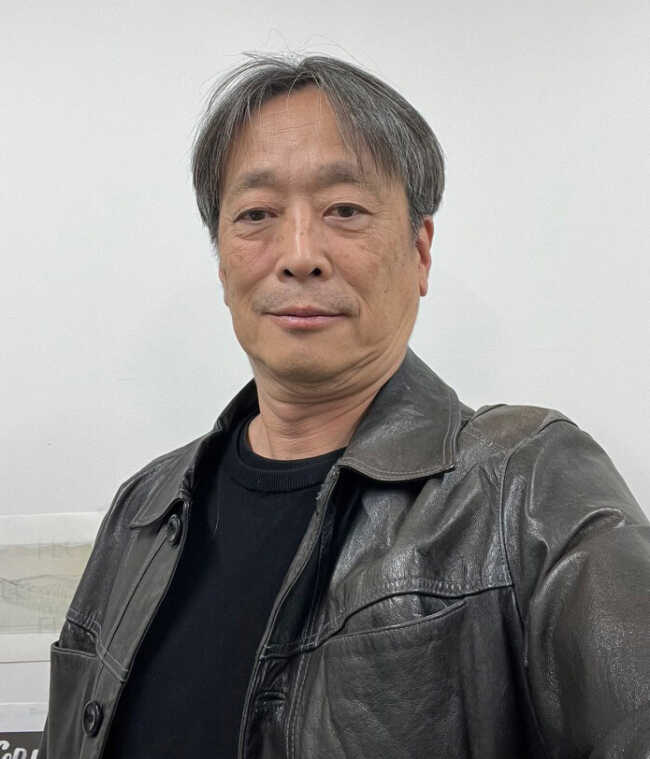Interview 2:Architect
家と地域の価値を高める「まちづくり」の試み
東北芸術工科大学教授の竹内昌義さんに「山形エコタウン前明石」のプロジェクトと、地域工務店によるまちづくりの将来と課題について、お話をうかがいました。
竹内 昌義 Takeuchi Masayoshi
1962年神奈川県生まれ。建築家。「みかんぐみ」共同代表。東北芸術工科大学デザイン工学部 建築・環境デザイン学科教授として山形エコタウン前明石のプロジェクトに携わる。専門は建築デザインとエネルギーで、建築の性能やまちづくりの視点をふまえながら保育園、エコハウス、オフィス、商業施設など、幅広い建物の設計を手がけている
地域工務店と取り組んだ
「野遊び」を提案する
分譲型エコタウンプロジェクト
ーこのプロジェクトはどのような経緯でスタートしたのでしょうか。
東北芸術工科大学に、地元山形の工務店である荒正さんからお声がけいただいたプロジェクトの一つが、このまちづくりでした。当初は学生を交えて企画を進めていましたが、実施設計の段階で私のほうで引き取りました。
敷地は山形市の施策に則って一区画200㎡以上。住宅の仕様は、荒正さんが加盟している北海道基準の高断熱・高気密住宅「ファースの家」の工法が条件でした。高性能なエコハウスは「内側に閉じた窓が小さい家」のイメージが付き物です。そこで「外へ開いたアクティブな家」であることをユーザーに分かりやすく伝えられたらと考え、アウトドアブランドのスノーピークさんにも入っていただくことになりました。

ー2018年の時点で「家での時間を楽しむ高性能なエコハウス」がコンセプトの分譲地というのは、時代を少し先取りしていますね。
確かに結果としてはそうなりますね(笑)。高い住宅性能に加え、僕らとしてはやはり、住宅で使われるエネルギーのことも考えたい。そこで全戸の屋根にソーラーパネルを設置する設計にもしました。
このエコタウンでは、住宅購入者の費用負担を減らすために、PPA(Power Purchase Agreement)を採用しています。これは太陽光発電の事業者が住人と電力購入契約を結び、発電した電気を供給する仕組みですが、実際、皆さん気に入って住んでいただいて、快適に暮らしていると聞いています。
ー「まち」をデザインするという点で、特に配慮したのはどんなことですか?
それは「ランドスケープ」ですね。家は一般に「南=表」と「北=裏」になりがちなので、ここでは、北側の裏通りに住民が安心して行き交うことができる緑豊かな小道を設け、裏にも家が開くようなプランにしました。
ランドスケープデザインでは、緑豊かな景観はもちろん、暮らしとのつながりが重要です。今回は幸い各戸の配置の関係性を僕たちが決められたので、景観としての美しさと、住民の皆さんの心理的な安全性の2つを両立できました。

ユーザーから支持された理由は
「価格」と「利便性」、
「ニーズに合ったコンセプト」
ー5年を経て、分譲した19区画のうち17区画が販売済み(2025年1月現在)となっていますが、住まい手から支持が得られた理由を竹内さんはどう考えていますか?
理由の一つはやはり「価格」でしょうか。大手ハウスメーカーの注文住宅と比べて圧倒的に安かったんですよ。「ファースの家」はHEAT20のG2レベルの断熱性能を備えた全館空調システム採用の建築工法で、仕様はハイスペック。一般的な「規格住宅」としては決して安くはありませんが、大手ハウスメーカーの注文住宅を検討している方々からすると「コストパフォーマンスが良い」という印象になったと思います。
また大きい小学校が近くにあるという教育環境や、買い物するお店が近くにあるなどの利便性の高さも一因といえるでしょう。
ー間取りプランにも特徴がありますね。


プランは「吹き抜けのある家」、「土間のある家」、「デッキテラスのある家」の3パターンから選べて、分譲開始時にはそれぞれを見学できるように準備しました。
一番人気は「吹き抜けのある家」。個人的には、2階にリビングがある「デッキテラスの家」が日射や風景を家の中に採り込みやすくて、住宅街での暮らしになじむのかなと思っています。
あとプランの設計では「住宅のリセールバリュー」を考慮しました。
ー「家を手放すときに売りやすくする」という視点ですか?
そうです。家って収納付きの玄関があって、LDKや水まわりがあって、寝室があって…と、構成要素はほとんど同じ。
自分たちらしさや暮らしに合わせた工夫を盛り込んだ注文住宅はもちろん魅力的ですが、「住宅のリセールバリュー」を重視するなら、どの家族でも暮らしやすいようにあまり突飛なことはしないほうがいい。だから3プランとも、汎用性の高いスタンダードな間取りを意識しました。
「戸建て住宅の集合地」はNG。
「誰と組んでどう進めるか」が
まちづくりの成功の鍵に
ー竹内さんは全国のさまざまな例に精通していらっしゃいますが、地域のビルダーや工務店が「まちづくり」に取り組む際に難しいのはどのような点でしょうか。
いろいろ見てきて感じるのは、地域工務店が手がける分譲地は「戸建て住宅の集合地」になってしまいがちだという点でしょうか。「ランドスケープ」への理解がもっと深まって、家々のつながりやまちとしての機能が上手にデザインされれば、魅力がもっと増すのにと思うことはよくあります。

これからは人口が減少し住宅着工件数も減っていく時代。地域工務店は、いろいろな分野の企業と組んで、住宅だけにこだわらずに業務を展開していく必要があると僕は考えています。
「山形エコタウン前明石」は分譲住宅地ですが、全国では地域工務店が主体となって施設や店舗まで含むまちづくりを担う例も出てきています。
ただ、まちのパブリックな機能の運用管理のノウハウが足りず、思ったようにまちづくりが進まないというケースが多いのも実情なので、工務店がまちづくりに取り組む際は、「誰と組んでどう進めるか」が成功の鍵を握っていると言えます。
ー地域工務店がまちづくりに取り組む意義やユーザー側のメリットを、竹内さんはどのように捉えていますか?
大手ハウスメーカーは、業績が悪くなれば会社ごと地域から撤退する可能性がありますが、工務店は地域に根づいた存在です。そもそも家は建ててからも不具合は出ますし、継続的なメンテナンスも必要です。
家の困りごとを相談する相手は、施工した工務店。その会社が地域をデザインして「まち」をつくることは、住まい手にとっては末永い暮らしの安心につながる大きなメリットです。また先々を考えると「価値の高いまち」に暮らすことは、土地や建物の資産価値を高めることにつながります。


工務店としても、これからのビジネスモデルは「建てて売っておしまい」では成り立ちません。多くの住民から「ここに住みたい!」と憧れられる付加価値の付いたまちと家を工務店が主導してつくることは、住まい手はもとより、地域全体にとっても意義のある大切な試みだと考えます。
(写真提供 株式会社 荒正)